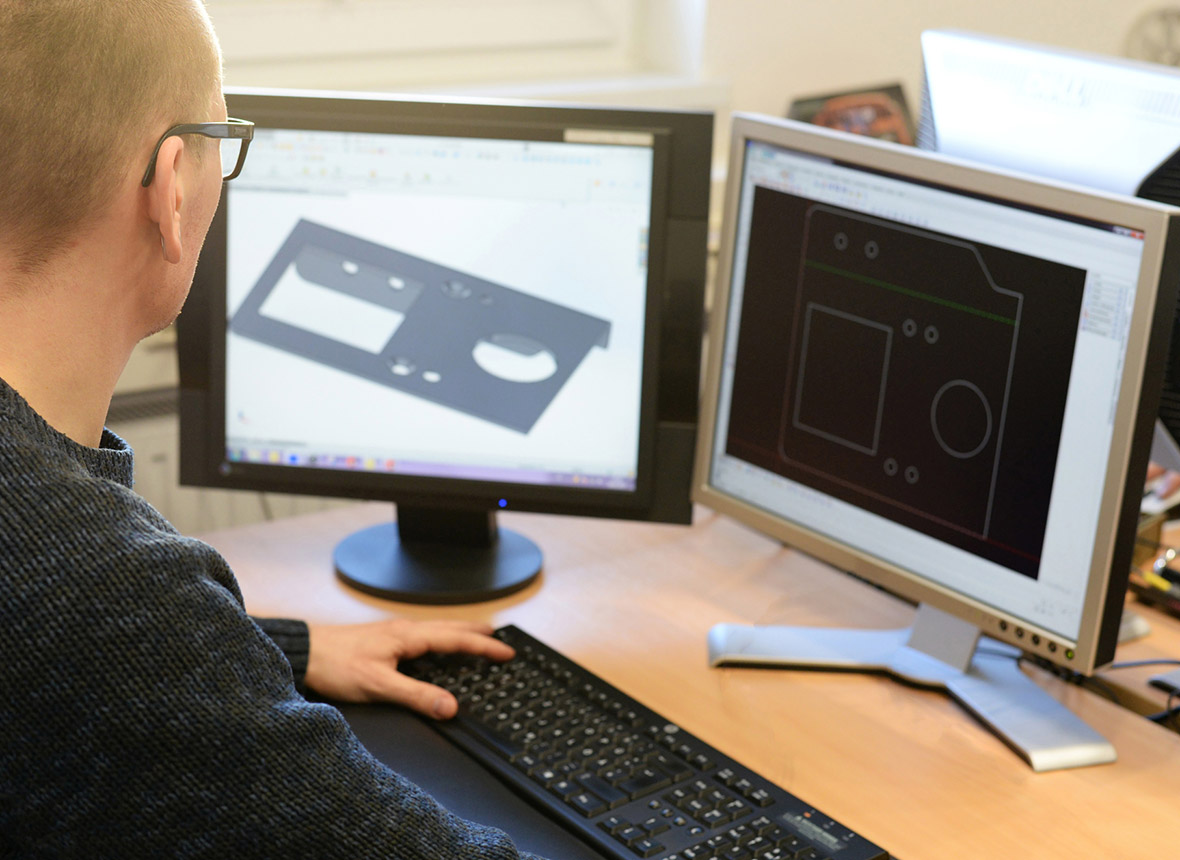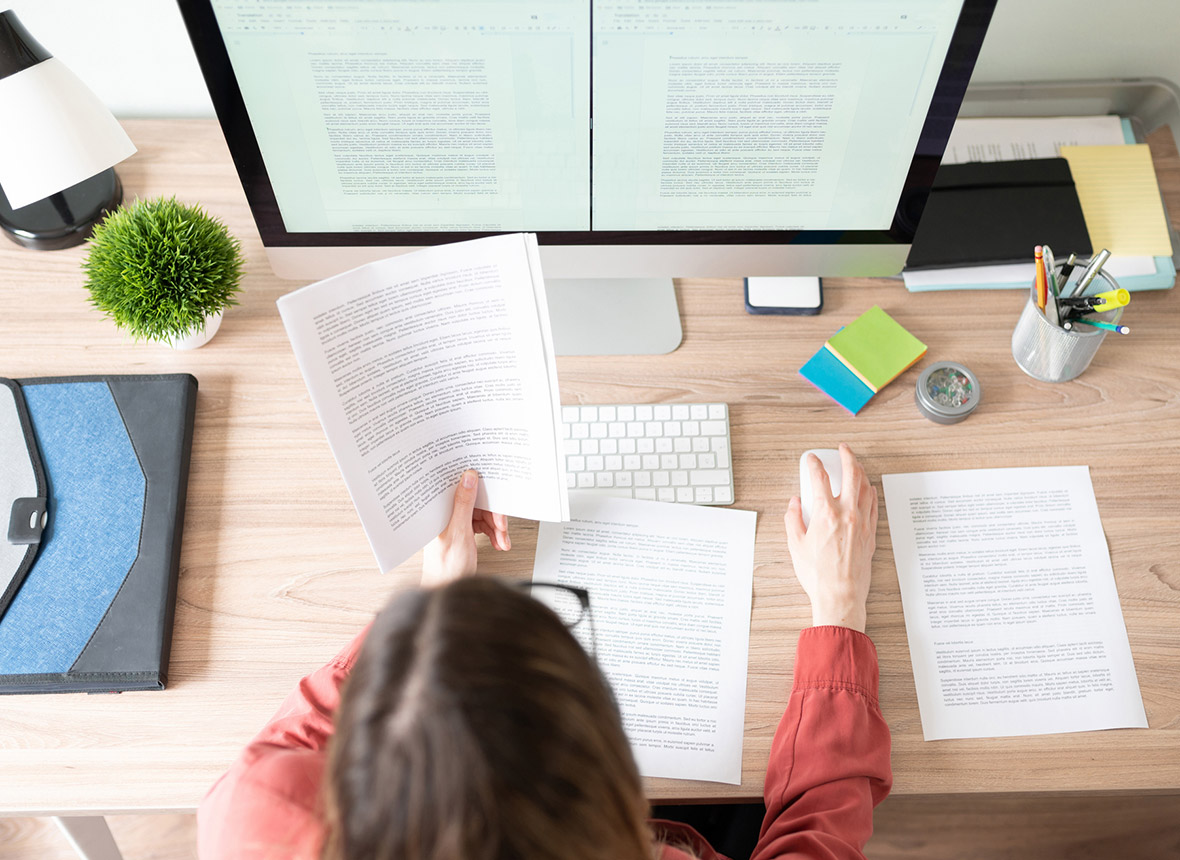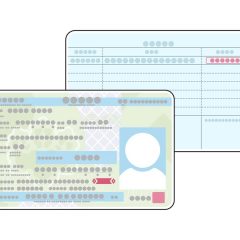日本で働く外国人の就労ビザ更新の手続き方法|必要書類から申請時期まで解説

日本で働く外国人社員が安心して就労を続けるためには、期限内に適切なビザ更新手続きを行うことが不可欠です。特に企業側は、在留期間の管理や必要書類の準備など、ビザ更新に関わる実務を正しく理解しておく必要があります。更新の遅れや不備があると、不許可による就労停止といったリスクにつながるため、注意が必要です。
本記事では、外国人の就労ビザ更新に関する基本的な知識から、申請時期、必要書類、入国管理局への提出方法まで、企業担当者が押さえるべきポイントを詳しく解説します。また、転職者採用時の手続きや更新不許可を防ぐ対応策についても紹介しています。ビザ更新業務に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
企業が押さえるべきビザ更新の基本知識

外国人社員の継続雇用において、就労ビザの更新手続きは企業が必ず理解しておくべき重要な業務です。更新申請の時期や手続きを誤ると、優秀な人材の不法滞在を招く可能性があります。
適切な在留期間管理と更新手続きの理解により、外国人社員が安心して働ける環境を整備できます。
在留期間更新許可申請の概要
在留期間更新許可申請とは、外国人が現在の在留資格を変更することなく、在留期間を延長して継続的に日本で活動するための手続きです。申請から許可までの標準的な審査期間は2週間から1か月程度ですが、繁忙期にはさらに時間がかかる場合があります。
審査では現在の活動と在留資格の整合性、上陸許可基準との適合性、素行、生計維持能力、雇用条件の適正性、納税状況が重点的に確認されます。
参考:法務省 出入国在留管理庁|在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
申請時期の管理方法
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前から提出可能です。6か月以上の在留期間を持つ外国人の場合、満了日のおおむね3か月前から申請できます。企業は外国人社員の在留期限を一覧表で管理し、申請時期を事前に把握することが重要です。
入院や長期出張など特別な事情がある場合には、3か月以上前からの申請も認められるため、該当する場合は事前に出入国在留管理局へ相談しましょう。
特例期間中の就労可否
在留期限内に更新申請を行った場合、審査期間中は最大2か月間の特例期間が適用されます。この期間中は在留カード裏面に「在留期間更新申請中」のスタンプが押され、現在の在留資格で就労を継続できます。
特例期間は許可を受け取った日、または在留期限から2か月経過した日のいずれか早い方まで有効です。新しい在留カードは必ずこの期限内に受け取る必要があり、企業は外国人社員への確実な連絡体制を整備することが求められます。
外国人社員のビザ更新に必要な書類と手続き

外国人社員のビザ更新を円滑に進めるためには、企業が適切な書類を準備し、正確な申請手続きを行うことが不可欠です。必要書類の不備や申請方法の誤りは、更新不許可や手続きの遅延を招く可能性があります。
企業の人事担当者は、法定調書合計表をはじめとする企業関連書類の準備から、申請書の記入方法、出入国在留管理局への提出まで、一連の手続きを体系的に理解する必要があります。
企業が準備する必要書類一覧
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印付き)が最重要で、電子申告時は受付完了メールも必要です。企業規模により四季報写しや決算書等が追加されます。
在留期間更新許可申請の必要書類
| 書類名 | 詳細・注意事項 |
| 在留期間更新許可申請書 | ・申請人用:本人が作成し署名
・所属機関作成用:会社が作成し押印 |
| 申請人の写真(4×3cm) | 3か月以内に撮影したもの(前回と同じ写真は不可) |
| 在職証明書 | 勤務先会社が発行 |
| 住民税課税証明書 | 1月1日時点で住所があった市区町村で取得 |
| 住民税納税証明書 | 納税状況を証明(未納がないことの確認) |
| 源泉徴収票 | 前年分の給与所得を証明 |
| 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | ・税務署受付印のあるもの(コピー可)
・電子申告の場合は受付完了メールも添付 |
| 在留カード | 提示(本人以外が申請する場合はコピー) |
| パスポート | 提示 |
参考:法務省 出入国在留管理庁|在留期間更新許可申請 申請書・必要書類・部数
転職者の場合は前職の源泉徴収票、退職証明書、活動内容・期間・地位・報酬が明記された雇用契約書等の追加書類が必要になります。
申請書の作成ポイント
在留期間更新許可申請書は「申請人用」を本人が作成して署名し、「所属機関作成用」を会社が作成して押印する分担制です。申請書には3か月以内に撮影した顔写真が必要で、前回と同じ写真は使用できません。
法務省ホームページから在留資格に応じた様式をダウンロードし、正確な記入を心がけましょう。記入日は当日のものを入れ、申請時に必要な印鑑や署名の確認も重要です。
入国管理局への提出方法
申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行い、整理券取得から数時間待ちの混雑が予想されます。申請時には在留カードとパスポートの原本提示が必要で、申請人本人が日本に滞在していることが条件です。
許可時の手数料は6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)**を収入印紙で納付します。書類不備を避けるため、事前に必要書類を十分確認してから申請しましょう。
※参考:法務省 出入国在留管理庁|在留手続等に関する手数料の改定
外国人の転職者採用時のビザ更新手続き

転職した外国人を採用する際のビザ更新手続きは、通常の更新とは大きく異なる複雑な対応が必要です。転職のタイミングや就労資格証明書の取得状況、職種変更の有無によって手続きが変わり、企業は適切な判断と準備が求められます。
特に転職直後の更新では、新しい会社での業務内容や雇用条件について詳細な書類提出と審査が行われるため、事前の準備が成功の鍵となります。
就労資格証明書の確認事項
就労資格証明書は転職先での就労が在留資格に適合するかを事前確認する制度で、取得により更新時の手続きが大幅に簡素化されます。取得済みの場合は通常の更新書類に証明書を添付するだけで済みますが、未取得の場合は新しい会社について在留資格取得時と同レベルの詳細審査が必要です。
在留期限まで2か月以内の転職では証明書取得の時間的余裕がないため、企業は詳細な資料準備を覚悟する必要があります。不交付の場合は更新不許可の可能性が高いため、早期の申請が重要です。
在留資格変更が必要なケース
前職と異なる職種に転職する場合は在留資格変更許可申請が必要です。学歴・職歴と新業務の整合性が重要で、たとえば情報系専門学校卒業者が翻訳通訳業務に就くことは原則できません。
転職時の手続きパターン
| ケース | 必要な手続き | 必要書類の特徴 |
| 同じ会社・同じ職種で更新 | 在留期間更新許可申請 | 通常の更新書類のみ |
| 転職済み+就労資格証明書取得済み | 在留期間更新許可申請 | 通常の更新書類+就労資格証明書 |
| 転職済み+就労資格証明書未取得 | 在留期間更新許可申請
(詳細審査) |
通常の更新書類+現在の会社の詳細資料 |
| 転職+前職と異なる職種 | 在留資格変更許可申請 | 変更申請書類一式+前職・現職の詳細資料 |
変更申請では新たな在留資格取得時と同等の審査が行われ、審査期間も2週間から1か月程度必要になります。
所属機関変更の届出手続き
転職時には契約機関に関する届出が法的義務として定められており、前職の退職日から14日以内と新職への入社日から14日以内にそれぞれ届出が必要です。届出方法は入国管理局窓口、郵送、インターネットから選択でき、転職の場合は両方を同時提出することも可能です。
届出を怠ると更新審査に悪影響を与えるため、更新申請前には必ず提出を完了させる必要があります。企業は転職者採用時にこの届出状況を確認し、未提出の場合は速やかな手続きを促すことが重要です。
ビザ更新不許可を防ぐための企業対応
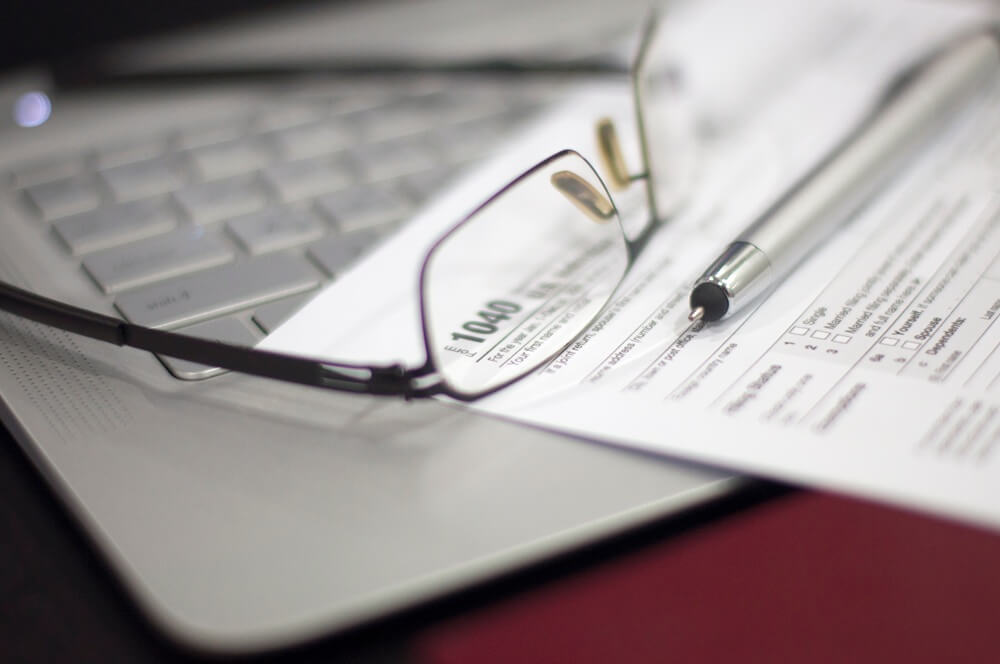
外国人社員のビザ更新不許可は企業にとって深刻な人材損失につながるため、事前の予防対策が極めて重要です。更新審査では外国人の在留状況が厳格にチェックされ、納税義務の履行状況、在留カードの適切な管理、素行の良否などが総合的に評価されます。
企業は単なる書類準備だけでなく、日常的な管理体制の構築と問題の早期発見・対処により、更新不許可のリスクを最小限に抑える必要があります。
納税状況の確認方法
住民税の課税証明書・納税証明書は毎年5月から6月に前年度分が発行されるため、この時期に取得し納税状況を確認することが重要です。税金滞納は更新審査でマイナス評価となり、特に留学生から採用した場合は学生時代の未納が発覚するケースが多いため注意が必要です。
本国に扶養者が多いなど正当な理由で非課税の場合は、事情を説明する文書を添付することで対応できます。企業は採用時に納税状況を確認し、滞納がある場合は速やかな納付を促すことが大切です。
在留カード管理の徹底
在留カード紛失時は速やかな再交付申請が法的義務であり、これを怠ると更新審査に悪影響を与えます。企業は在留カードのコピーを保管し、有効期限や記載内容を定期的に確認する体制を構築すべきです。資格外活動や在留資格に適合しない業務への従事は不法就労となるため、業務内容と在留資格の整合性を常に監視する必要があります。
人事担当者は外国人社員の在留カード管理状況を定期的にチェックし、問題が発生した場合は即座に適切な対応を取ることが重要です。
長期出張時の注意事項
ビザ更新の申請時と新しい在留カード受取時は、外国人本人が必ず日本に滞在している必要があります。申請完了後は海外出張が可能ですが、許可通知や追加書類要請への迅速な対応体制を整備することが不可欠です。1年の半分以上を海外で過ごす場合は出入国在留管理庁から説明を求められるため、業務上の必要性を証明する説明書を事前に準備しておく必要があります。
企業は海外出張の多い外国人社員について、出張理由や期間を詳細に記録し、更新申請時の証明資料として活用できるよう準備することが重要です。
企業の申請取次制度活用とサポート体制
 外国人社員のビザ更新手続きを効率的に進めるためには、企業が申請取次制度を活用し、適切なサポート体制を構築することが重要です。申請取次承認を取得すれば企業職員が代理申請を行えるため、外国人社員の業務時間確保と手続きの確実性向上が期待できます。
外国人社員のビザ更新手続きを効率的に進めるためには、企業が申請取次制度を活用し、適切なサポート体制を構築することが重要です。申請取次承認を取得すれば企業職員が代理申請を行えるため、外国人社員の業務時間確保と手続きの確実性向上が期待できます。
更新費用の負担ルールや外部専門家への依頼基準を明確にし、企業として一貫した対応方針を確立することで、外国人社員が安心して働ける環境を提供できます。
申請取次承認の取得方法
申請取次承認は公益財団法人入管協会が実施する研修会を受講することで取得でき、企業職員が外国人社員の代理でビザ申請を行えるようになります。承認を受けた企業職員は本人に代わって出入国在留管理局での申請手続きが可能になるため、外国人社員の業務負担を大幅に軽減できます。
研修会のスケジュールは変更される場合があるため、入管協会のホームページで最新情報を定期的に確認し、計画的な受講申し込みを行うことが重要です。承認取得により企業の人事体制が強化されます。
更新費用の負担ルール
ビザ更新手数料6,000円の負担については法的な定めがなく、企業の方針によって決定すべき事項です。企業が雇用継続を期待して外国人社員に更新手続きを求める場合は、企業負担が妥当と考えられます。行政書士への委託費用を含めた予算計画を立てる際は、更新対象者数と手続きの複雑さを考慮し、年間コストを算出することが重要です。
費用負担ルールを就業規則や雇用契約書に明記し、外国人社員との間で事前に合意を得ることで、後のトラブルを防止できます。
外部専門家への依頼基準
行政書士への依頼は入管での長時間待機(整理券取得から数時間)を回避し、書類不備によるリスクを大幅に低減できるメリットがあります。複雑な転職案件、初回更新、複数名の同時申請などは専門家への依頼が効果的です。
外国人社員の業務時間を確保し、確実な更新許可を得るためには、専門家の活用が重要な選択肢となります。企業は申請の複雑度と社内リソースを総合的に判断し、効率的な手続き体制を構築することで、人材の安定確保と業務の継続性を両立できます。
まとめ
外国人社員の就労ビザ更新は、企業の人材確保と法的リスク回避において極めて重要な手続きです。基本的な申請時期と必要書類の把握から始まり、転職者特有の手続き、不許可要因の事前防止、申請取次制度の活用まで、体系的な対応が求められます。企業は外国人社員の在留期間を適切に管理し、必要に応じて専門家を活用することで、確実な更新許可取得と安定した雇用継続を実現できます。適切な準備と管理体制により、優秀な外国人人材の長期雇用が可能になります。