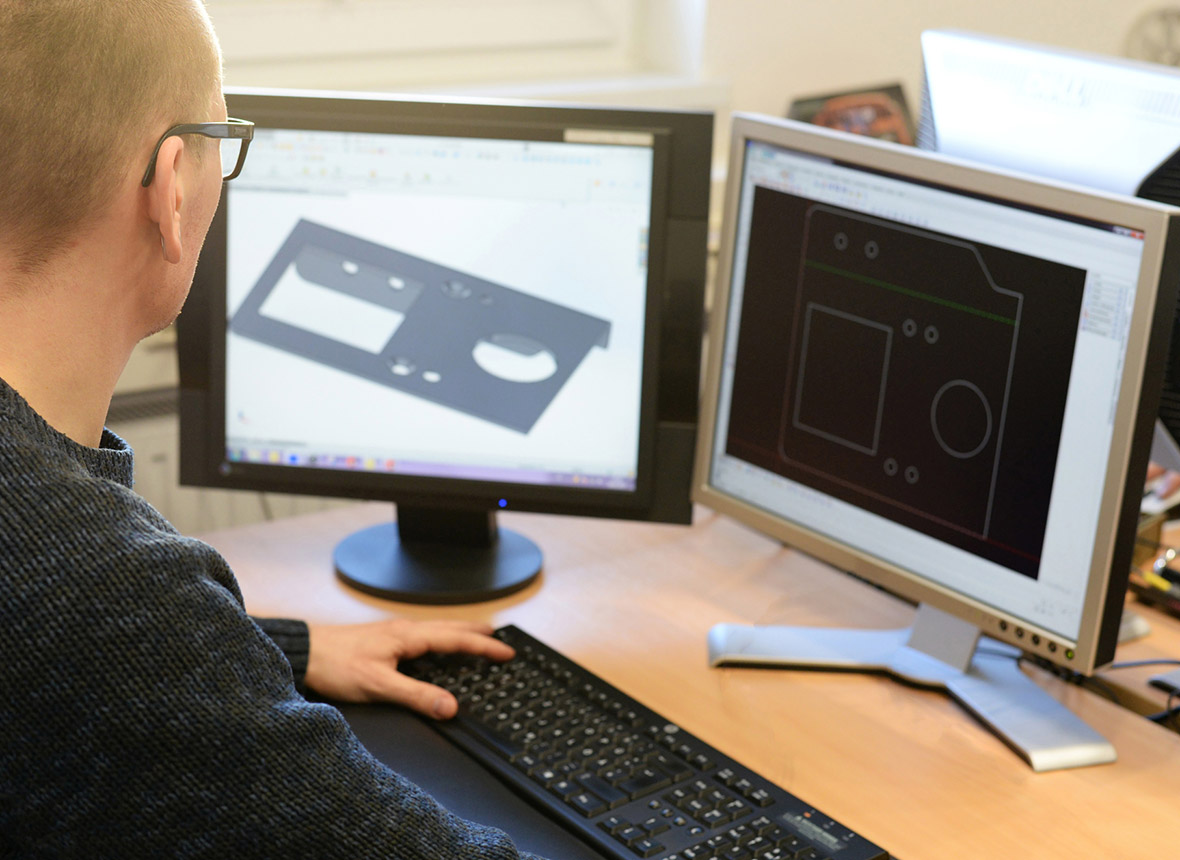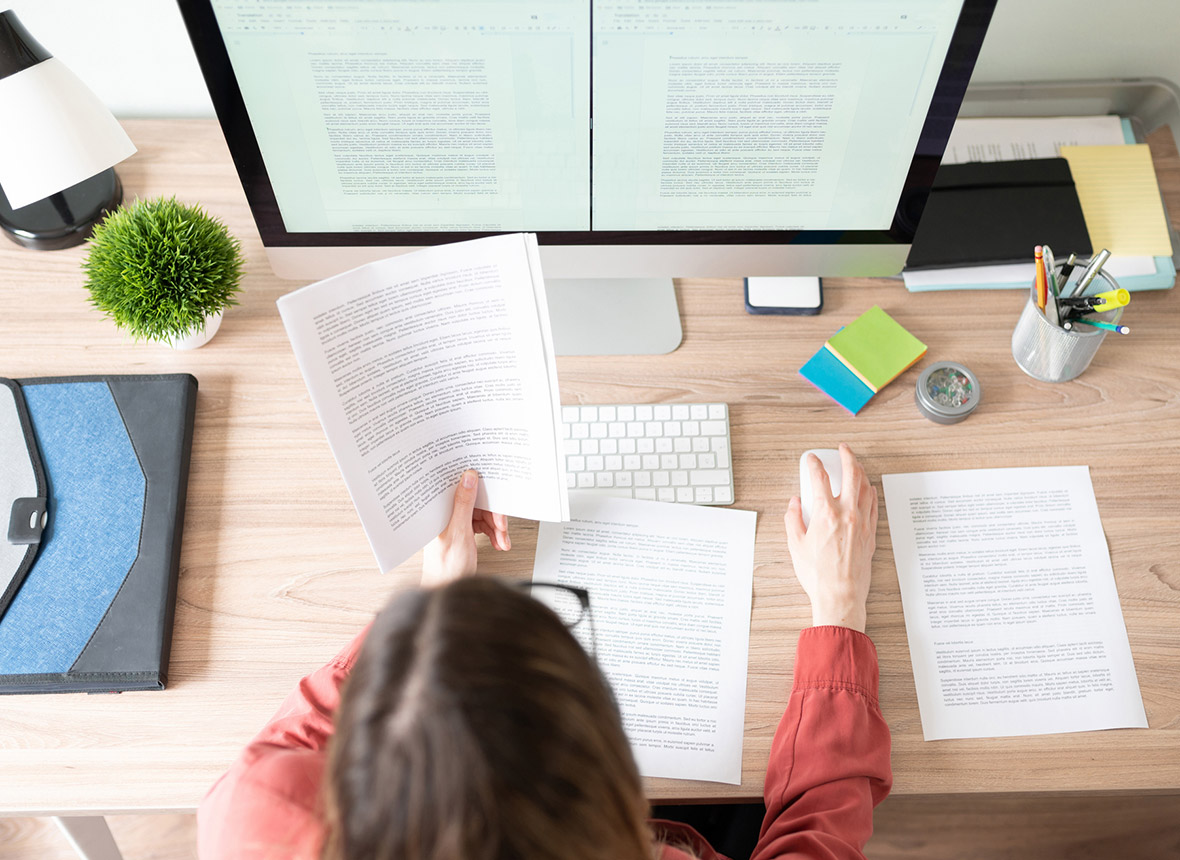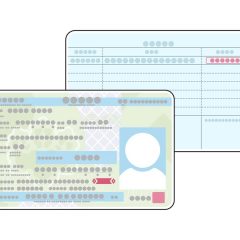特定技能とは?制度内容や技能実習との違い・採用方法をわかりやすく解説

深刻化する人手不足を背景に、日本では即戦力となる外国人材の受け入れ制度が整備されてきました。その中でも「特定技能制度」は、一定の技能や日本語能力を有する外国人が、特定の業種で働くことを目的とした新しい在留資格として注目を集めています。しかし、「特定技能とは何か」「技能実習制度とはどう違うのか」「採用にはどのような手続きが必要か」といった疑問を抱える企業担当者も少なくありません。
本記事では、特定技能制度の概要から、特定技能1号・2号の違い、対象となる分野、取得の流れ、技能実習制度との比較、さらには採用・受け入れの手続きや企業側のサポート義務までを解説します。外国人材の雇用を検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
特定技能制度の概要と成り立ち

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を背景に創設された外国人材受け入れのための制度です。この制度により、特定の産業分野において一定の技能を持つ外国人が日本で働くための在留資格が整備されました。
ここでは特定技能制度の基本的な内容や成り立ち、最新の改正点について解説します。
特定技能とは何か?制度の目的と背景
特定技能とは、2019年に創設された在留資格で、人材を確保することが困難な産業分野において外国人により不足する人材の確保を図るための制度です。この在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分けられています。
1号は相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を、2号は熟練した技能を要する業務に従事する活動を対象としています。日本国内の深刻な労働力不足という社会的背景のもと、単に安価な労働力を確保するためではなく、即戦力となり得る外国人材を受け入れる仕組みとして設計されました。
特定技能制度が創設された経緯と時期
特定技能制度は2019年4月に正式に運用が開始されました。それまでの外国人労働者受け入れ制度では対応しきれない人手不足という課題に対応するため、新たな在留資格として特定技能が設けられたのです。
制度創設当初は介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業の12分野が対象でした。この制度により、より幅広い産業分野で外国人材の受け入れが可能となり、日本の労働市場における人材不足の緩和が期待されるようになりました。
2025年最新の制度改正ポイント
2025年3月11日に開催された「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、特定技能制度の分野別運用方針に関する重要な改正が閣議決定されました。主な改正点として、介護分野では従来認められていなかった訪問系サービスへの特定技能外国人の従事が可能となりました。
また、工業製品製造業分野では、外国人材の適正かつ円滑な受け入れを推進するための民間団体が設立され、受け入れ機関にはこの団体への加入が条件付けられることになりました。外食業分野においても、風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労が認められるようになり、従事可能な業務範囲が拡大されています。
参考:出入国在留管理庁|特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)
特定技能の種類と基本構造

特定技能制度では、外国人材を受け入れるための在留資格として「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類が設けられています。両者には求められる技能レベルや在留期間、家族帯同の可否など重要な違いがあります。
これらの違いを理解することで、企業側は適切な人材確保の計画が立てられ、外国人労働者は自身のキャリアパスを描くことが可能となります。
特定技能1号と2号の基本的な違い
特定技能1号と2号は、求められる技能レベルや滞在条件に大きな違いがあります。1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ人材を対象とし、基本的な業務遂行能力を求めています。
一方、2号は「熟練した技能」を持ち、現場での管理指導能力も必要とされる上位レベルの在留資格です。両者の違いを理解することで、企業にとっても外国人労働者にとっても、より適切な選択ができるようになります。
| 項目 | ||
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
| 在留期間 | 1年、6か月、4か月ごとの更新で、通算で上限5年まで | 3年、1年、6か月ごとの更新で、上限なし |
| 家族帯同 | 認められていない | 要件を満たせば認められる(配偶者、子) |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |
| 支援義務 | 企業または登録支援機関による支援の対象 | 支援の対象外 |
| 日本語レベル | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
| 永住権取得 | できない | 要件を満たせば取得可能 |
| 雇用形態 | 直接雇用(農業と漁業のみ派遣可能) | 直接雇用(農業と漁業のみ派遣可能) |
特定技能1号は幅広い分野での就労が可能で、基礎的な技能と日本語能力があれば取得できることから、外国人材の日本での就労の入口として機能しています。対して2号は、より高度な技能を持ち長期的に日本での就労を希望する外国人向けの制度といえるでしょう。
在留期間と更新の仕組み
特定技能1号と2号では、在留期間や更新の仕組みが大きく異なります。特定技能1号の在留期間は通算5年が上限で、4カ月・6カ月・1年ごとに更新が必要となります。この上限は「特定技能1号で在留できる期間が通算で5年以内である必要」に基づいています。
そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合もあります。一方で、特定技能2号は更新回数に上限がなく、6カ月・1年・3年ごとの更新により、長期的な在留が可能となっています。
家族帯同と永住権取得の可能性
特定技能1号では家族帯同が認められていない一方、特定技能2号では一定の要件を満たせば配偶者や子どもの帯同が可能となります。特定技能2号で家族帯同が認められる主な要件としては、適切な収入があること、安定した住居を確保していることなどが挙げられます。
また、永住権取得についても重要な違いがあります。特定技能1号では直接的な永住権取得のルートはないのに対し、特定技能2号では一定期間の在留と安定した収入などの要件を満たすことで永住権申請が可能になります。このように、特定技能2号は長期的な日本での生活を視野に入れた外国人にとって大きなメリットがあります。
特定技能で就労可能な分野と業務範囲

特定技能制度では、日本国内で人手不足が深刻とされる特定の産業分野においてのみ外国人材の受け入れが認められています。現在、特定技能1号では16分野、特定技能2号では11分野が対象となっており、分野ごとに就労可能な業務内容や必要とされる技能レベルが定められています。これらの分野は関係省庁によって所管され、それぞれの特性に合わせた運用がなされています。
| 分野名 | 管轄省庁 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 主な業務内容 |
| 介護 | 厚生労働省 | ○ | × | 身体介護、生活支援等の介護業務 |
| ビルクリーニング | 厚生労働省 | ○ | ○(2023年追加) | 建築物内部の清掃作業 |
| 工業製品製造業 | 経済産業省 | ○ | ○(2023年追加) | 金属加工、電子部品製造、機械部品組立等 |
| 建設 | 国土交通省 | ○ | ○ | 型枠施工、鉄筋施工、とび、左官等 |
| 造船・舶用工業 | 国土交通省 | ○ | ○ | 溶接、塗装、加工、組立等 |
| 自動車整備 | 国土交通省 | ○ | ○(2023年追加) | 日常点検、定期点検、分解整備 |
| 航空 | 国土交通省 | ○ | ○(2023年追加) | 空港グランドハンドリング、航空機整備 |
| 宿泊 | 国土交通省 | ○ | ○(2023年追加) | フロント、客室清掃、レストランサービス等 |
| 農業 | 農林水産省 | ○ | ○(2023年追加) | 耕種農業、畜産農業 |
| 漁業 | 農林水産省 | ○ | ○(2023年追加) | 漁業、養殖業 |
| 飲食料品製造業 | 農林水産省 | ○ | ○(2023年追加) | 食品加工、製造、品質管理等 |
| 外食業 | 農林水産省 | ○ | ○(2023年追加) | 調理、接客 |
| 自動車運送業 | 国土交通省 | ○(2024年追加) | × | 貨物自動車の運転業務 |
| 鉄道 | 国土交通省 | ○(2024年追加) | × | 車両や線路の保守・点検・整備 |
| 林業 | 農林水産省 | ○(2024年追加) | × | 植林、下刈り、間伐等の森林作業 |
| 木材産業 | 農林水産省 | ○(2024年追加) | × | 製材、木材加工等 |
参考:出入国在留管理庁|特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
特定技能1号の対象16分野の詳細
特定技能1号では現在16の産業分野で外国人材の受け入れが認められています。制度創設当初の2019年4月には12分野でスタートし、2024年には新たに4分野が追加されました。各分野によって求められる技能や業務内容は異なり、雇用形態についても特徴があります。
特に注目すべき点は、16分野のうち農業と漁業の2分野のみが派遣での雇用が認められている点です。その他の14分野については直接雇用が原則となっています。
| 分野名 | 導入時期 | 所管省庁 | 主な業務内容 | 雇用形態 |
| 介護 | 2019年(制度創設時) | 厚生労働省 | 身体介護、生活支援等 | 直接雇用のみ |
| ビルクリーニング | 2019年(制度創設時) | 厚生労働省 | 建築物内部の清掃 | 直接雇用のみ |
| 工業製品製造業 | 2019年(制度創設時) | 経済産業省 | 金属加工、電子部品製造等 | 直接雇用のみ |
| 建設 | 2019年(制度創設時) | 国土交通省 | 型枠施工、鉄筋施工等 | 直接雇用のみ |
| 造船・舶用工業 | 2019年(制度創設時) | 国土交通省 | 溶接、塗装、組立等 | 直接雇用のみ |
| 自動車整備 | 2019年(制度創設時) | 国土交通省 | 点検整備、車検整備等 | 直接雇用のみ |
| 航空 | 2019年(制度創設時) | 国土交通省 | グランドハンドリング等 | 直接雇用のみ |
| 宿泊 | 2019年(制度創設時) | 国土交通省 | フロント、客室清掃等 | 直接雇用のみ |
| 農業 | 2019年(制度創設時) | 農林水産省 | 耕種農業、畜産農業 | 派遣可能 |
| 漁業 | 2019年(制度創設時) | 農林水産省 | 漁業、養殖業 | 派遣可能 |
| 飲食料品製造業 | 2019年(制度創設時) | 農林水産省 | 食品加工、製造等 | 直接雇用のみ |
| 外食業 | 2019年(制度創設時) | 農林水産省 | 調理、接客 | 直接雇用のみ |
| 自動車運送業 | 2024年追加 | 国土交通省 | 貨物自動車の運転 | 直接雇用のみ |
| 鉄道 | 2024年追加 | 国土交通省 | 車両・線路の保守点検 | 直接雇用のみ |
| 林業 | 2024年追加 | 農林水産省 | 植林、間伐等 | 直接雇用のみ |
| 木材産業 | 2024年追加 | 農林水産省 | 製材、木材加工等 | 直接雇用のみ |
参考:出入国在留管理庁|特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
各分野には独自の技能試験があり、これらに合格することが特定技能1号の在留資格取得の条件となります。また、農業と漁業分野で派遣雇用が認められているのは、これらの分野での季節変動や地域的特性に配慮した措置となっています。
特定技能2号の対象11分野とその特徴
特定技能2号の対象分野は当初、建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に新たに9分野が追加され、現在は11分野となっています。注目すべき点として、介護分野は特定技能2号の対象外となっています。
これは介護分野には別途「介護福祉士」という国家資格に基づく在留資格があるためです。特定技能2号では各分野で「熟練した技能」と「現場管理能力」が求められ、実務経験の要件も設定されています。
| 分野名 | 導入時期 | 所管省庁 | 要求される技能水準 | 日本語能力要件 | 実務経験要件 |
| ビルクリーニング | 2023年追加 | 厚生労働省 | 熟練した清掃技能と現場管理能力 | 不要 | 管理・指導経験2年以上 |
| 工業製品製造業 | 2023年追加 | 経済産業省 | 高度な製造技能と工程管理能力 | 不要 | 管理・指導経験2年以上 |
| 建設 | 制度創設時(2019年) | 国土交通省 | 熟練した建設技能と現場管理能力 | 不要 | 建設現場での実務経験10年以上 |
| 造船・舶用工業 | 制度創設時(2019年) | 国土交通省 | 高度な造船技能と工程管理能力 | 不要 | 造船業での実務経験5年以上 |
| 自動車整備 | 2023年追加 | 国土交通省 | 高度な整備技術と診断能力 | 不要 | 整備現場での実務経験3年以上 |
| 航空 | 2023年追加 | 国土交通省 | 専門的な航空業務技能と安全管理能力 | 不要 | 航空業務での実務経験3年以上 |
| 宿泊 | 2023年追加 | 国土交通省 | 高度な接客スキルとホテル運営能力 | 不要 | ホテル業での管理職経験2年以上 |
| 農業 | 2023年追加 | 農林水産省 | 農業経営・生産管理の専門知識と技能 | 不要 | 農業での管理職経験3年以上 |
| 漁業 | 2023年追加 | 農林水産省 | 漁業・養殖業の専門知識と技能 | JLPT N3以上 | 漁業での実務経験3年以上 |
| 飲食料品製造業 | 2023年追加 | 農林水産省 | 食品製造の専門技術と品質管理能力 | 不要 | 食品製造業での管理職経験2年以上 |
| 外食業 | 2023年追加 | 農林水産省 | 調理技術と店舗運営能力 | JLPT N3以上 | 外食業での管理職経験2年以上 |
参考:出入国在留管理庁|特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
特徴的なのは、外食業と漁業分野では日本語能力試験N3以上の日本語能力が求められる点です。これは接客や安全管理上の理由からと考えられます。また、各分野によって要求される実務経験の年数が異なり、建設分野では10年以上という長期の経験が必要とされる一方、多くの分野では2〜3年程度の管理・指導経験が条件となっています。
特定技能の取得方法と必要な要件
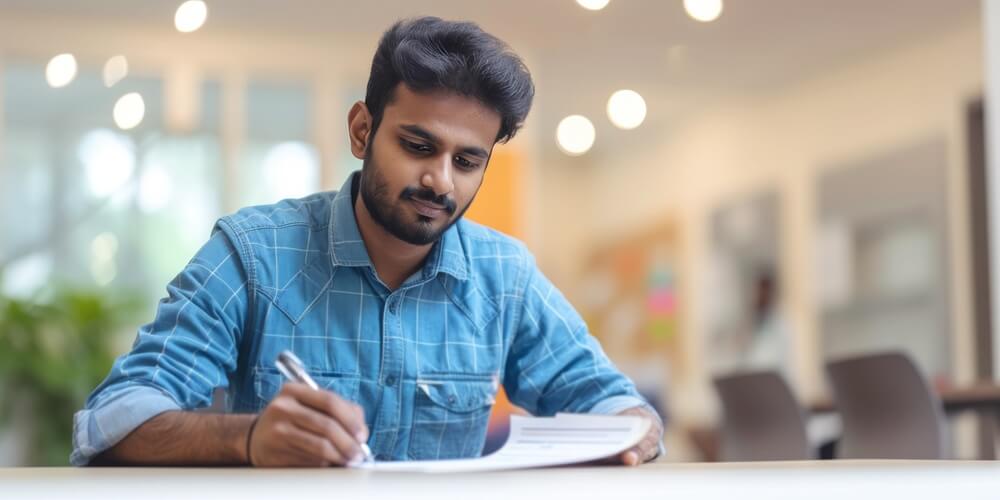
特定技能の在留資格を取得するには、いくつかのルートと条件が設定されています。特定技能1号と2号では取得要件や試験内容が異なり、外国人材がどのようなキャリアパスを描くかによって最適な取得方法も変わってきます。
以下では、特定技能の取得方法と必要な要件について詳しく解説していきます。
特定技能1号の取得ルートと条件
特定技能1号を取得するには、主に2つのルートがあります。1つ目は各分野の技能試験と日本語試験に合格するルートです。この場合、特定技能1号の対象分野における技能試験と、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)で一定以上のスコアを取得する必要があります。
2つ目は技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号へ移行するルートです。このルートでは、技能実習2号を良好に修了していることが条件となりますが、日本語試験が免除されるメリットがあります。また、技能実習と特定技能の職種に関連性がある場合は、技能試験も免除されます。
初めて日本で働く外国人には試験合格ルート、既に技能実習で日本での就労経験がある方には移行ルートが有利といえるでしょう。
技能試験と日本語能力試験の概要
特定技能1号の取得には、原則として技能試験と日本語能力試験の両方に合格する必要があります。技能試験は分野ごとに異なり、それぞれの所管省庁が指定する試験実施機関によって実施されます。たとえば、介護分野は厚生労働省、建設分野は国土交通省が所管しており、試験内容や難易度も分野によって大きく異なります。
一方、日本語能力については、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)で200点以上(250点満点中)の取得が必要です。N4レベルは基本的な日本語を理解できるレベルとされており、日常会話や基本的な漢字を読めることが求められます。これらの試験は国内だけでなく海外でも実施されており、母国から直接応募することも可能となっています。
特定技能2号への移行条件と要件
特定技能1号から2号へ移行するためには、各分野の特定技能2号評価試験に合格する必要があります。この試験は1号とは異なり、熟練した技能と現場管理能力が求められる高度なものとなっています。
外食業分野を例にとると、2年以上の管理・指導経験(副店長やサブマネージャーなど)が必要であり、試験はマークシート方式で「接客全般」「飲食物調理」「衛生管理」「店舗運営」などの内容から出題されます。特徴的なのは、外食業と漁業分野では日本語能力試験N3以上が必須となる点です。
また、試験申し込みは個人ではなく企業を通じて行う必要があるという1号とは異なる条件も設けられています。特定技能2号は長期的に日本での就労を希望する熟練技能者向けの制度であり、キャリアアップを目指す外国人労働者にとって重要な選択肢となっています。
技能実習と特定技能の明確な違い
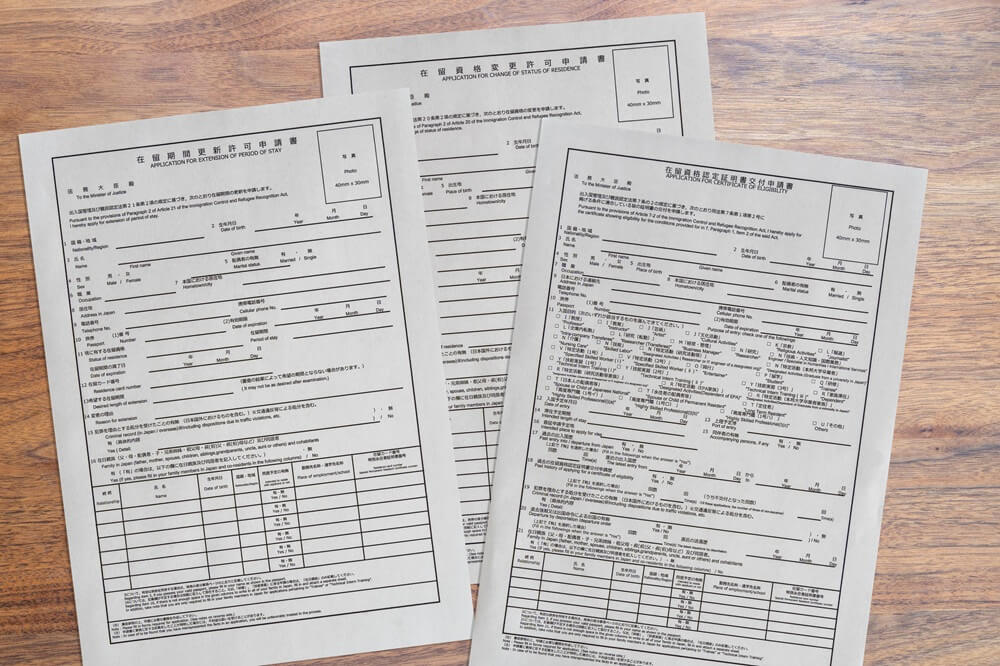
特定技能と技能実習は名称が似ているため混同されやすい制度ですが、その目的や仕組みには重要な違いがあります。両制度を正しく理解することで、企業は自社のニーズに合った適切な外国人材活用の選択ができ、外国人労働者も自身のキャリアプランに沿った在留資格を選ぶことができます。ここでは両制度の違いについて明確に解説します。
| 項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 日本の人材不足の解消 |
| 職種・作業 | 91職種(168作業)に限定
※2025年4月時点 |
16業種(特定技能1号)、11業種(特定技能2号) |
| 在留期間 | 技能実習
|
特定技能1号:通算5年まで
特定技能2号:上限なし |
| 転職の可否 | 原則不可(場合によって「転籍」は可能) | 同一職種であれば転職が可能 |
| 家族帯同の可否 | 不可 | 特定技能1号:不可
特定技能2号:配偶者と子供のみ可能 |
| 受け入れに関与する団体 | 監理団体、送り出し機関、技能実習機構 | 特になし(登録支援機関への委託は任意) |
| 受け入れ人数制限 | あり | 原則なし(介護と建設分野は例外) |
| 技能水準 | 特になし(介護のみ日本語能力試験N4が必要) | 基礎的な知識や経験、日本語能力が必要 |
| 単純労働の可否 | 不可(技術の習得が目的) | 可能(人手不足解消が目的) |
| 永住権取得の可能性 | 技能実習のままでは不可能 | 特定技能1号→2号→永住者というルートあり |
参考:出入国在留管理庁|外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組、外国人技能実習制度について
制度目的と位置づけの根本的な違い
技能実習制度と特定技能制度の最も根本的な違いは、その制度目的にあります。技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を主目的としており、開発途上国等の外国人が日本で技術やノウハウを学び、帰国後に母国の発展に貢献することを目指しています。
そのため、技術の習得に重点が置かれ、帰国が前提となっています。一方、特定技能制度は「日本の人材不足対策」という労働政策的側面を持ち、外国人を労働力として受け入れることを正面から認めた制度です。この目的の違いが、在留期間の設定や転職の可否、家族帯同といった実務的な違いの基盤となっています。
国際的な位置づけを見ても、技能実習は国際協力の一環として、特定技能は労働力確保の手段として、まったく異なる文脈で運用されているのです。
就労可能な業務範囲の違い
技能実習生と特定技能外国人が従事できる業務範囲には大きな違いがあります。技能実習制度では対象が91職種(168作業)に限定され、技術習得が目的であるため単純労働は認められていません。これに対し特定技能では、単純労働を含む幅広い業務への従事が可能となっています。
たとえば、外食業は技能実習では対象外ですが、特定技能では調理や接客業務などに従事することができます。また、技能実習と特定技能の両方に含まれる分野でも、特定技能の方がより幅広い業務に従事できるケースが多いのが特徴です。
技能実習では技術の習得と移転に焦点が当てられるため業務が限定的ですが、特定技能では人手不足解消という目的から、より実用的かつ多様な業務への従事が認められているのです。
転職・家族帯同・在留期間の比較
技能実習と特定技能では、外国人の就労環境や生活条件に大きな違いがあります。技能実習生は原則として実習先の変更(転職)ができないのに対し、特定技能外国人は同一職種内であれば転職が可能です。
これにより、特定技能外国人はより自由に労働条件の良い職場を選べる立場にあります。家族帯同についても、技能実習生は家族を呼び寄せることができませんが、特定技能2号の外国人は配偶者と子どもの帯同が認められています。在留期間については、技能実習制度が最長で5年(技能実習1号から3号まで合計)であるのに対し、特定技能1号も通算5年ですが、特定技能2号に移行すれば上限なく更新が可能となります。
特に注目すべき点として、特定技能は「特定技能1号→2号→永住者」というルートで永住権取得の可能性があるのに対し、技能実習のままでは永住権取得は困難です。
企業が特定技能外国人を受け入れるための条件

特定技能外国人を雇用するためには、企業側にもいくつかの重要な条件を満たすことが求められます。適切な受け入れ体制の整備や支援計画の策定は、外国人材の定着やスムーズな業務遂行のために欠かせません。また、場合によっては登録支援機関への委託も必要となります。
ここでは、特定技能外国人の受け入れに関する企業側の要件や準備について解説します。
受入れ企業に求められる基本要件
特定技能外国人を雇用するためには、まず企業が特定産業分野に該当していることが前提条件となります。特定技能制度は人手不足が深刻な特定の産業分野のみを対象としているため、該当分野以外の企業では活用できません。また、2024年6月14日からは対象の協議会への加入が必須となっており、この点も注意が必要です。
分野によっては、受け入れ可能な業態や細かな要件が設定されている場合もあります。賃金条件については、同じ仕事をする日本人と同等以上の給与水準を確保することが求められており、安価な労働力確保を目的とした制度ではないことを理解しておく必要があります。
技能実習生を雇用している企業では、技能実習2号よりも特定技能外国人の給与を高く設定することも求められています。
特定技能外国人へのサポート義務
特定技能1号の外国人を雇用する企業には、「1号特定技能外国人支援計画」の作成と実施が義務付けられています。この支援計画には、以下の支援内容を含める必要があります。
- 事前ガイダンスの提供(職務内容、労働条件、生活環境等の説明)
- 出入国する際の送迎(空港への出迎え、住居までの送迎等)
- 適切な住居の確保に係る支援(住居探しの補助、契約手続きの支援等)
- 生活に必要な契約に係る支援(銀行口座開設、携帯電話契約等の補助)
- 公的手続き等への同行(社会保障、税金などの手続きの同行等)
- 生活オリエンテーションの実施(日本の生活ルール、医療機関情報等の提供)
- 日本語学習の機会の提供(日本語教室の情報提供、学習教材の提供等)
- 相談・苦情への対応(労働条件や生活上の問題等への対応)
- 日本人との交流促進に係る支援(地域行事への参加促進等)
- 非自発的離職時の転職支援(次の就職先に関する情報提供等)
- 定期的な面談の実施・行政機関への通報(3か月に1回以上の面談実施等)
これに対し、特定技能2号の外国人に対しては支援義務がありません。これは2号の外国人は既に日本での生活に慣れており、より自立した生活が可能と考えられているためです。
登録支援機関の役割と活用方法
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国在留管理局から認定を受けた機関です。過去2年間に外国人の在籍がない企業は、自社で支援を行うことができず、登録支援機関への委託が必須となります。
重要なポイントとして、委託する場合は支援業務の全てを委託する必要があり、一部だけを委託することはできません。一部でも省略すると法令違反となるため注意が必要です。登録支援機関を選ぶ際は、経験豊富で実績のある機関を選ぶことが望ましく、支援内容や費用について事前によく確認しておくことが大切です。
支援業務の委託費用は機関によって差があるため、複数社から見積もりを取ることをおすすめします。
特定技能外国人の採用方法と手続きの流れ

特定技能外国人を採用する方法は、大きく「国内にいる外国人を採用する方法」と「海外から採用する方法」の2つに分けられます。どちらの方法にも固有の手続きがあり、必要な書類や準備も異なります。企業側は採用したい人材の状況に応じて適切な方法を選び、法的手続きを漏れなく行うことが重要です。
ここでは、特定技能外国人の具体的な採用手順とそれぞれのポイントについて解説します。
国内にいる外国人を特定技能で採用する方法
すでに日本国内にいる外国人を特定技能として採用する場合、主に技能実習生や留学生からの移行が考えられます。技能実習2号を良好に修了した外国人の場合、同じ分野の特定技能へ移行する際に日本語試験が免除されるメリットがあります。また、技能実習で行っていた職種・作業と特定技能の業務に関連性が認められれば、技能試験も免除される場合があります。
一方、留学生からの移行では、特定技能の試験に合格する必要がありますが、学歴と業務の関連性を問われない点が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なります。在留資格変更申請には、特定技能雇用契約書や支援計画書などの書類が必要となり、最寄りの出入国在留管理局で手続きを行います。この方法なら、既に日本での生活や就労経験がある人材を採用できるため、スムーズな就労開始が期待できるでしょう。
海外から特定技能外国人を採用する流れ
海外にいる外国人を特定技能として採用する場合は、まず対象者が現地で特定技能の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。これらの試験は各国で実施されていますが、国によって実施状況や対象分野が異なるため、最新情報の確認が必要です。
試験合格後、企業と外国人との間で雇用契約を締結し、企業は出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請が許可されると、在留資格認定証明書が発行され、外国人はこれをもとに在外日本大使館でビザ(査証)を申請します。ビザが発給されたら来日し、上陸審査を経て特定技能外国人として就労が可能となります。
この一連の流れには人材派遣会社や送り出し機関を活用することも多く、特に初めて外国人を採用する企業にとっては、これらの専門機関のサポートを受けることで手続きがスムーズに進みやすくなります。
採用時に必要な書類と手続きのポイント
特定技能外国人の採用には、いくつかの重要な書類と手続きが必要です。在留資格認定証明書交付申請には、申請書、写真、返信用封筒に加え、「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」に基づく書類が必要となります。
具体的には、申請人に関する書類(技能試験・日本語試験の合格証明書など)、所属機関に関する書類(特定技能所属機関概要書、登記事項証明書など)、分野に関する書類(特定分野の要件確認書類)などが含まれます。また、特定技能1号外国人を雇用する場合は支援計画書の作成が必須で、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住居確保支援など10項目の支援内容を記載する必要があります。
申請書類は分野によって異なる場合があるため、出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の様式を確認することが重要です。書類作成においては、記載漏れや不備がないよう注意し、必要に応じて行政書士など専門家のサポートを受けることもおすすめします。
特定技能制度の受け入れ企業のメリットと課題

特定技能制度は人材不足対策として外国人労働者を受け入れる制度ですが、企業側にとってのメリットと課題の両面を理解しておくことが重要です。単純労働を含む幅広い業務に従事できるというメリットがある一方で、受け入れ費用や体制整備など乗り越えるべき課題もあります。
また、技能実習制度から育成就労制度への移行など、外国人材の受け入れ制度は常に変化しているため、最新動向を把握することも欠かせません。
特定技能外国人を雇用するメリット
特定技能外国人を雇用する最大のメリットは、単純労働を含む幅広い業務に従事できる点です。従来、単純労働に従事できる資格は永住者などの身分に基づいた在留資格に限られていたため、採用できる人材の数は限定的でした。
対して特定技能は学歴や関連業務の従事経験が求められないため、外国人材側のハードルが低く、人材の出現率も高くなっています。さらに、技能実習制度が廃止され育成就労制度が施行されることで、育成就労から特定技能へのキャリアパスが明確になり、外国人材がより日本での就労を選びやすい環境が整いつつあります。
特定技能2号の対象分野も拡大し、家族帯同が可能になることで、優秀な人材の定着も期待できます。これらに加え、外国人材を受け入れることで企業のグローバル化が促進され、訪日外国人への対応力も向上するという副次的なメリットも見逃せません。
受け入れにおける費用と体制の課題
特定技能外国人を雇用する際に直面する課題として、費用面の問題が挙げられます。人材紹介会社への手数料、登録支援機関への支援委託費用、必要書類の翻訳費用、住居確保のための初期費用など、さまざまなコストが発生します。
これらの費用負担は、特に資金力に限りのある中小企業にとって大きなハードルとなることがあります。また、言語や文化の違いによるコミュニケーション上の課題も重要です。業務指示や安全管理、生活面でのサポートなど、日常的なやり取りにおいて誤解や行き違いが生じないよう配慮する必要があります。
これらの課題に対処するためには、登録支援機関の選定を慎重に行い、必要に応じて通訳サービスを活用することが有効です。また、同じ出身国の外国人を複数名採用することで、相互サポートの体制を構築し、コミュニケーションの問題を軽減することも一つの方法です。
技能実習制度廃止と育成就労制度の関係性
技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を目的としていましたが、実際には労働力として利用される実態や、技能実習生の失踪増加、過酷な労働環境などの問題が指摘されてきました。こうした背景から技能実習制度は見直しが行われ、廃止されることが決まりました。
代わりに新設される「育成就労制度」は、特定技能制度への移行を前提とした在留資格で、3年間で特定技能1号に移行できるだけのスキルを育成することを目指しています。この制度は単なる技術習得だけでなく、労働力としての雇用・就労も明確に位置づけられており、特定技能の対象分野と育成就労制度の対象分野が一致するよう整備されています。
育成就労で2年間就労した後、特定技能1号で5年間、さらに特定技能2号に移行すれば更新制限なく就労を続けることができ、家族も呼び寄せられるというキャリアパスが確立されつつあります。この変化は外国人材にとって日本で働くことの魅力を高め、企業にとっても採用の機会拡大につながることが期待されています。
まとめ
特定技能制度は、日本の人手不足解消と外国人材の安定的な就労環境の両立を目指す在留資格です。特定技能1号と2号の違いを理解し、適切な分野選択と必要な要件を把握することが重要です。企業側は受け入れ体制の整備と支援義務を果たしながら、外国人材にとっては明確なキャリアパスが見えるこの制度を活用することで、持続可能な労働環境の構築が可能となります。技能実習制度から育成就労制度への移行という変化も踏まえ、適切な外国人材の採用と活用を進めることで、企業の競争力強化と多様な価値観の取り込みが実現できるでしょう。