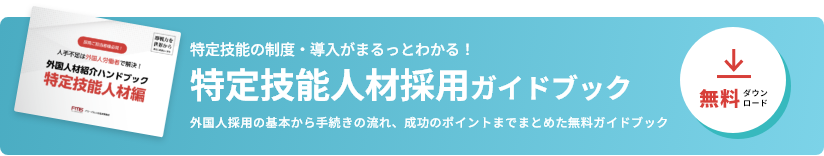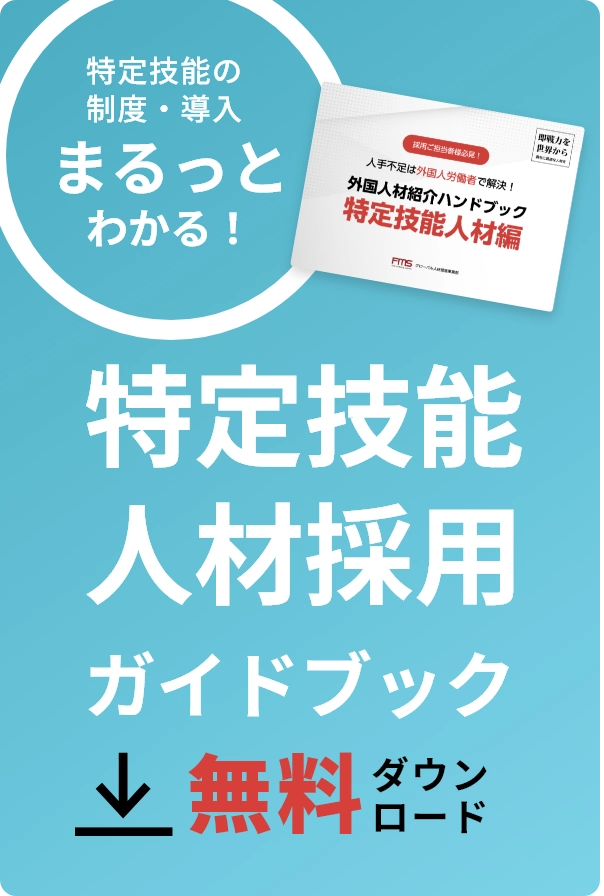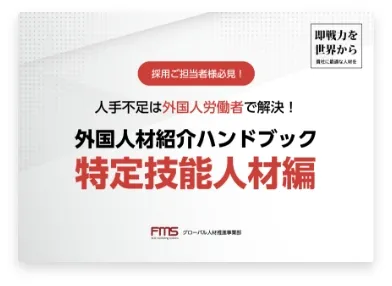特定技能2号とは?取得条件や業種・試験内容・1号との違いを解説

外国人材の長期的な活用を見据えた制度として注目されているのが、「特定技能2号」です。2019年に創設された特定技能制度の中でも、2号はより高度な技能や経験を有する人材を対象としており、在留期間の更新が無制限である点や、家族の帯同が認められる点が大きな特徴です。しかし、取得には一定の実務経験や専門試験の合格など、厳格な条件が定められており、1号との違いや対象業種なども正しく理解する必要があります。
本記事では、特定技能2号の概要から、取得要件や試験情報、各業種ごとの基準、企業側の受け入れ体制までをわかりやすく解説。外国人材の戦力化を進めたい企業担当者や制度を詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能2号とは

特定技能2号は、日本の深刻な人手不足分野において熟練した技能を持つ外国人材に長期就労の機会を提供する在留資格です。
2019年に創設された特定技能制度の上位区分にあたり、特定技能1号より広範な権利が与えられます。具体的には、在留期間の無期限更新や家族帯同の許可など、より安定した生活基盤を築くことができる点が特徴的です。
当初は建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に対象が11分野へと拡大され、現在では農業や外食業、工業製品製造業など幅広い産業で活用されています。
外国人にとっては永住につながる道筋となり、企業側にとっては長期的な人材確保とマネジメント層の育成という双方にメリットをもたらす制度といえるでしょう。
特定技能2号の定義と概要
特定技能2号とは、人手不足が深刻な産業分野において外国人の就労を認めた在留資格「特定技能」の上位区分です。現場でリーダーシップを発揮できる豊富な実務経験を持つ人材を対象とし、特定技能1号より広範な権利が付与されます。
当初は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象でしたが、2023年には11分野へと大幅に拡大されました。介護分野については、特定技能1号からステップアップする別の在留資格「介護」が既に設けられているため、特定技能2号の対象外となっています。
特定技能1号と2号の主な違い
特定技能1号と2号には、以下の7つの重要な違いがあります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年(更新あり)通常は短期間ごとの更新 | 上限なしより長期の更新期間 |
| 永住許可申請 | 原則不可 | 一定条件下で申請可能 |
| 求められる技能 | 基本的な業務知識と経験 | 高度な専門技能と管理能力 |
| 外国人支援体制 | 企業による支援計画必須 | 支援計画不要 |
| 家族同伴 | 原則認められない | 条件付きで配偶者・子の帯同可 |
| 日本語要件 | 基本的な日本語能力必要 | 多くの分野で不問(一部必要) |
| 試験実施 | 広く国内外で実施 | 主に国内で限定的に実施 |
特定技能1号には通算5年という明確な在留期限がありますが、特定技能2号ではこの制限が撤廃され、条件を満たす限り何度でも更新が可能です。また、特定技能2号では家族の帯同が認められるほか、永住権取得への道も開かれています。
さらに、1号では義務付けられている支援計画の策定・実施が2号では不要となり、企業側の負担も軽減されます。
特定技能2号の対象となる11分野
特定技能2号が適用される産業分野は、以下の11分野です。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
介護分野が対象外となっている理由は、同分野では既に特定技能1号からのキャリアアップ先として在留資格「介護」が設けられているためです。このように、各分野の特性に応じた制度設計がなされています。
特定技能2号を取得するメリット
特定技能2号の取得は、外国人労働者と企業双方に多くのメリットをもたらします。
- 在留期間の更新回数が無制限であること
- 要件を満たせば家族帯同が可能になること
- キャリアステップが明確になり、キャリア形成ができること
- 永住権取得のための条件を満たせる可能性があること
日本での永住を視野に入れている外国人にとって、特定技能2号は大きな魅力を持つ在留資格です。家族と共に暮らせることで、心理的な安定を得られるだけでなく、日本社会への定着もスムーズになります。
雇用する企業側も、長期的な人材確保というメリットに加え、外国人労働者の管理・教育体制の強化にも繋がります。特定技能2号の外国人は、他の外国人社員への指導や日本人スタッフとの橋渡し役として活躍が期待できるため、多文化共生の職場づくりに貢献します。
特に、多数の外国人を雇用している事業所では、同じ文化的背景を持つリーダーの存在が、コミュニケーション上の課題解決に大きな役割を果たすでしょう。
特定技能2号の取得条件と申請要件
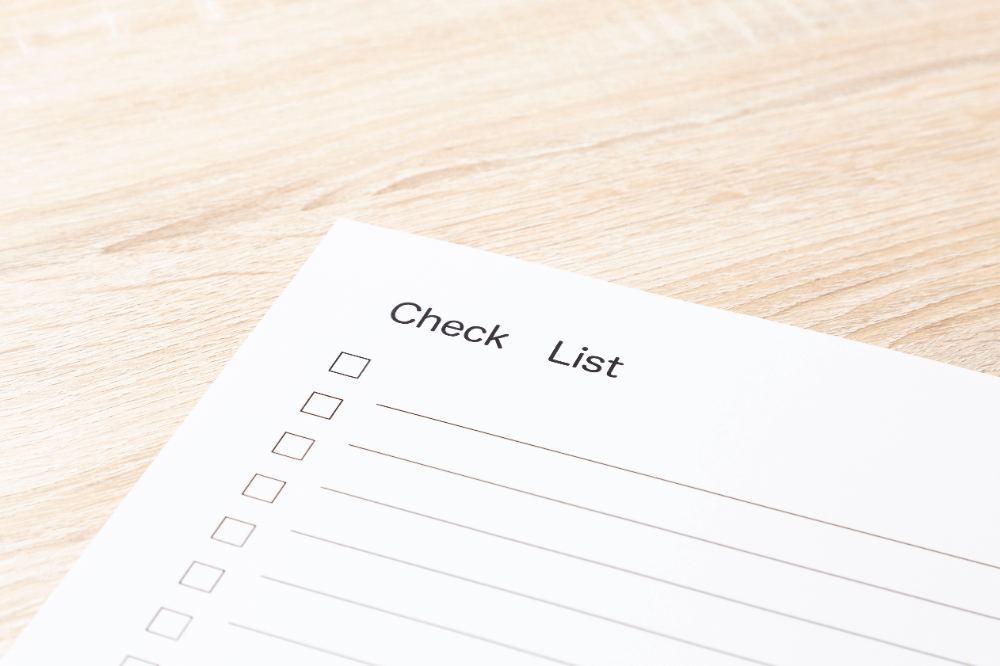
特定技能2号の取得を目指す外国人労働者や受入企業が知っておくべき条件と申請要件について解説します。この在留資格は単なる滞在期間の延長だけでなく、家族帯同や永住の可能性など多くの権利が得られる制度ですが、その分、取得には高いハードルが設定されています。
以下では基本的な取得要件から実務経験、日本語能力、そして家族帯同の条件までを解説します。
特定技能2号の基本的な取得要件
特定技能2号の在留資格を申請するには以下の要件を満たす必要があります。
- 各分野の特定技能2号試験への合格(分野によっては別試験も可)
- 実務経験の要件(管理指導経験など内容は分野ごとに異なる)
- 一部の分野での日本語能力要件
現時点(2024年9月)では多くの分野で特定技能2号の試験がスタートしています。受験資格を得るためにも一定の要件が設けられており、管理・指導などの実務経験が求められます。
分野ごとに要件のレベルは異なりますが、いずれも試験合格と実務経験の両方が必須となる点が共通しています。
実務経験に関する条件と証明方法
大半の分野において、特定技能2号取得には2年以上の実務経験が要求されます。求められる経験内容は「複数の作業員を指導しながら作業に従事する」「工程を管理する」といった責任あるポジションでの業務です。
具体例として、外食業では副店長やサブマネージャーとしての2年間の実績が、飲食料品製造業ではライン長や班長として複数の作業員を指導する2年以上の経験が必須とされています。
実務経験を証明するには、現職や前職の企業からの証明書が必要です。在留期限に余裕がない場合向けに、外食業や飲食料品製造業などでは期間短縮の経過措置も設けられているため、詳細を確認しておくと良いでしょう。
日本語能力に関する要件
日本語能力については、分野によって要件が大きく異なります。漁業と外食業の2分野では、日本語能力試験(JLPT)N3以上という明確な基準が設けられています。
一方、その他の多くの分野では公式な日本語能力試験が要件に含まれていません。しかしながら、実際の試験は日本語で行われ、特定技能1号の試験とは違って漢字にルビがつかないケースが多いため、実質的にはある程度の日本語力が必要です。
職場での管理・指導を担当するポジションとなることを考慮すると、公式な要件がない分野でも、実務上は高いレベルのコミュニケーション能力が求められるのが現実といえるでしょう。
家族帯同の条件と手続き
特定技能2号の大きな魅力は家族帯同が認められる点です。条件を満たせば、配偶者と子どもを日本に呼び寄せることが可能になります。帯同のための主な要件は、正式な婚姻関係を証明できる書類の提出と、家族全員の生活を支えるだけの十分な経済力があることの証明です。
これらの条件を満たせば、家族にも適切な在留資格が発行されます。
注意すべき点として、親や兄弟、その他の親戚は帯同対象にならないことがあります。特定技能1号では原則として家族帯同が不可であることを考えると、この2号での家族帯同の許可は外国人労働者にとって非常に重要なメリットといえるでしょう。
特定技能2号の試験情報と分野別要件

特定技能2号への申請を検討している方にとって、試験情報と分野別の要件を知ることは非常に重要です。産業分野ごとに試験内容や難易度、必要な実務経験が大きく異なるため、自分の該当分野に特化した情報収集が欠かせません。
ここでは、試験の基本情報から主要分野の具体的要件、そして各分野の試験実施状況まで解説します。まずは各分野の試験実施機関と問い合わせ先を下表でご確認ください。
| 産業分野 | 試験実施機関 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| ビルクリーニング | 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 | https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu |
| 工業製品製造業 | 経済産業省 | https://www.sswm.go.jp/exam/about-ssw2/ |
| 建設 | 一般社団法人 建設技能人材機構 | https://jac-skill.or.jp/exam/ |
| 造船・舶用工業 | ClassNK | https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/ |
| 自動車整備 | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会 | https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/ |
| 航空 | 公益社団法人 日本航空技術協会 | https://exam.jaea.or.jp/ |
| 宿泊 | 一般社団法人 宿泊業技能試験センター | https://caipt.or.jp/tokuteiginou/aab |
| 農業 | 一般社団法人 全国農業会議所 | https://asat-nca.jp/asat2 |
| 漁業 | 一般社団法人 大日本水産会 | https://suisankai.or.jp/skill/ |
| 飲食料品製造業 | 一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構 | https://otaff1.jp/howto_corp/ |
| 外食業 | 一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構 | https://otaff1.jp/howto_corp/ |
特定技能2号評価試験の概要
現在、大半の分野で特定技能2号の試験がすでに実施されています。これらの試験は基本的に日本語で行われ、特定技能1号の試験とは異なりルビ付きではないため、相応の日本語能力が不可欠となるでしょう。さらに、受験資格として一定の実務経験が要件となっている点も注目すべきです。
申込方法については分野ごとに異なり、外食業や飲食料品製造業のように企業からしか申し込めない分野が多く存在します。最新かつ詳細な試験情報は、各実施機関のウェブサイトで随時確認することが大切です。
飲食料品製造業の試験内容と要件
飲食料品製造業で特定技能2号を取得するには、「飲食料品製造業 特定技能2号技能測定試験」に合格し、複数作業員の指導と工程管理の2年以上の実務経験が求められます。「複数の作業員」とは2名以上の技能実習生やアルバイト、特定技能外国人を指し、「工程管理」はライン長や班長などの役職を意味します。
日本語のみでの試験実施となり、ルビはありません。在留期限の残りが少ない方向けに経過措置も用意されており、最短1年の実務経験で申請可能なケースもあります。申込は企業経由のみ可能で、詳細は農林水産省サイトに掲載されています。
建設・製造業分野の試験内容と要件
建設分野では、特定技能2号評価試験か技能検定1級への合格が求められます。加えて、建設現場で班長・職長として複数人を指導しながらの実務経験も必須条件となっています。この実務経験年数は区分ごとに0.5~3年と幅があるため、個別に確認する必要があるでしょう。
製造業分野においては、「ビジネス・キャリア検定3級」と「製造分野特定技能2号評価試験」の両方への合格、または「技能検定1級」の取得が求められます。3年以上の実務経験も必要です。製造分野は「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分に分類され、対応する試験が設定されています。
その他分野の試験実施状況と難易度
各分野の試験要件は多岐にわたります。外食業と漁業では日本語能力試験N3以上が必須条件となっていますが、その他の分野でも実質的な日本語力が求められる点は共通しています。
農業分野の試験難易度は「実務経験7年以上の人の3割が合格する水準」と設定されており、かなり高度な専門性が試されることがわかります。
| 分野 | 主な特徴・要件 |
|---|---|
| 外食業 | • 「外食業特定技能2号技能測定試験」合格 • JLPT N3以上必須 • 2年間の実務経験(副店長等) |
| 農業 | • 特定技能2号技能試験合格(耕種/畜産) • 複数従業員指導+2年実務経験 または • 3年以上の実務経験 |
| ビルクリーニング | • 評価試験または1級技能検定合格 • 現場管理の2年以上実務経験 |
| 造船・舶用工業 | • 2号試験と技能検定1級両方合格 • 監督者として2年以上の実務経験 |
| 自動車整備 | • 2号評価試験または2級技能検定合格 • 評価試験ルート:3年以上の経験 • 技能検定ルート:実務経験不問 |
| 航空 | • 区分により試験内容異なる • 空港グランドハンドリング:現場指導経験 • 航空機整備:専門的作業3年以上 |
| 宿泊 | • 宿泊分野特定技能2号評価試験合格 • 複数従業員指導+2年以上実務経験 |
| 漁業 | • 2号漁業技能測定試験合格 • JLPT N3以上必須 • 区分ごとに実務要件異なる |
特定技能2号取得の実務ガイド

特定技能2号の取得は、日本でのキャリア形成と長期滞在を望む外国人材にとって重要なステップです。この資格は単なる滞在延長だけでなく、家族帯同や将来的な永住への道を開くものでもあります。一方、受入企業側も優秀な人材の長期確保という観点から、特定技能2号への理解を深める必要があるでしょう。
特定技能1号から2号への移行プロセス
特定技能1号から2号へと移行するには、戦略的なキャリア計画が不可欠です。
基本的な流れは以下のとおりです。
- 実務経験の蓄積(多くは2年以上、管理・指導経験)
- 実務経験証明書の準備(企業の協力が必要)
- 特定技能2号試験の申し込みと受験
- 試験合格後の在留資格変更申請
特定技能1号の在留期限(通算5年)を考慮し、余裕をもった準備が肝心です。転職経験がある場合は、前職企業からの証明書も必要となるため、退職時にも良好な関係維持を心がけましょう。計画性と人間関係が成功の鍵となります。
特定技能2号取得にかかる費用と期間
特定技能2号取得には、試験料と証明書発行料という2種類の費用がかかります。産業分野により金額差が大きいため、事前に正確な情報を把握しておくことが重要です。
| 分野 | 受験料(税込) | 合格証明書交付手数料 |
|---|---|---|
| 外食業 | 14,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |
| 飲食料品製造業 | 15,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |
| 製造分野 | 15,000円 | 15,000円 |
| 宿泊 | 15,000円 | 12,100円(企業が納付) |
| ビルクリーニング | 16,500円 | 11,000円 |
| 農業 | 15,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |
| 漁業 | 15,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |
| 自動車整備 | 4,800円 | 16,000円 |
| 建設 | 2,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |
| 造船・舶用工業(溶接) | 96,800円(最低料金) | - |
全体の取得期間は実務経験2年に加え、試験準備や申請手続きを含めると最短でも2年半程度必要です。不合格時は追加費用を覚悟し、合格証明書の取得方法も事前確認が必須となります。
申請時の注意点と企業の役割
特定技能2号申請を成功させるポイントは以下のとおりです。
- 試験の申込は企業が行う分野が多い
- 実務経験の要件(多くが2年以上)を満たすための計画的なキャリア形成の必要性
- 前職の企業からの実務経験証明が必要な場合がある
- 企業との良好な関係性の重要性
企業側には、実務経験証明書の発行、試験申込の手配、退職者からの証明依頼への対応など重要な役割があります。経済産業省は「実務経験書の交付依頼には対応すべき」と明確に示しており、この協力なくして2号取得はほぼ不可能と言えるでしょう。
特定技能2号の今後の展望と課題
特定技能2号は対象分野の拡大(2→11分野)により大きな転換期を迎えています。多くの外国人材が2号取得を希望する中、企業側の受入体制整備が競争力に直結する時代となりました。外国人採用市場では「2号取得支援」が企業選択の重要基準になりつつあります。
現状では2号在留者はわずか37人(2023年12月末)ですが、1号保有者は20万人超と潜在需要は膨大です。今後5年間で2号在留者は劇的に増加すると予測され、早期に体制を整えた企業が人材確保で優位に立つでしょう。持続的な成長には2号視点のキャリアパス設計が鍵となります。
まとめ
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材に向けた上位資格であり、在留期間の無制限更新や家族帯同、将来の永住権取得への道を開くという大きなメリットがあります。一方で、各業種の試験合格と実務経験(多くは管理職として2年以上)の両方が求められる高いハードルも存在します。取得成功の鍵は企業の全面的な協力と計画的な準備にあり、実務経験証明や試験申込のサポートが不可欠となるでしょう。対象11分野での試験はすでに実施中で、今後は特定技能1号から2号へのステップアップを目指す外国人材が増加すると予想されます。